2025年度 第3回成人講座
健康講話「骨骨(コツコツ)つづける健康づくり-骨を守って健康長寿-」
8月27日(水)午後1時30分より当館大会議室において、健康講話「骨骨(コツコツ)つづける健康づくり-骨を守って健康長寿-」を実施しました。参加者は34名、役員7名の計41名でした。
講師は、JA愛知厚生連 保健福祉事務局 保健福祉事業部 健康増進支援グループ 保健師 天野早紀さんにお願いし、骨粗しょう症についてをはじめ、骨折の起こしやすい部位など6つの項目について、保健師の立場から丁寧に分かりやすく説明していただきました。
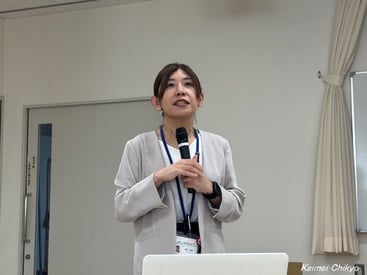
①骨粗しょう症ってどんな病気?
- 骨の量が減り、質も劣化して、骨折を起こしやすくなった状態のこと。
- 骨代謝の仕組みには、破骨細胞(骨吸収:古くなった骨を破壊する)の働きが骨芽細胞(骨形成:新しい骨を作る)の働きを上回り骨量が減ると骨粗しょう症になります。
②骨折を起こしやすい部位
- 肩の付け根、手首、背骨、太ももの付け根など。特に太ももの付け根は「介護」を必要とする部位にあたります。
- また、高齢者に多くみられる骨折の一つに、背中や腰が曲がることで、気づかないうちに、骨粗しょう症による背骨の骨折が起きる「圧迫骨折」があります。その症状は、吐き気、食欲不振、息苦しさ、呼吸機能低下などがあります。特に体や身長の変化に注意しましょう。(定期健診で身長が毎年低くなっていたら、圧迫骨折のサイン!)
③骨が弱くなる原因は?
- 取り除けない原因(自己管理できない)として、加齢、性別(女性・閉経)、遺伝、骨折経験、体型などがあります。加齢とともに骨・筋力等が衰える。 取り除ける原因(自己管理できる)として、喫煙、過度な飲酒、運動不足、偏った食生活などがあげられます。
④運動で骨を守ろう
- 毎日定期的に運動しましょう。ウォーキングや片脚立ち、座って脚上げ、背筋運動など、無理をせず各自に見合った時間・回数等で行いましょう。
⑤生き生きとした骨を作る食事
- 基本は3度の食事をバランス良く‼
(主食)ごはん、パン、麺類などの炭水化物
(主菜)肉・魚・卵・大豆製品などのおかず
(副菜)野菜・きのこ・海草などのおかず
※1日の中で、乳製品と果物を各1品プラスしよう! - カルシウム(骨の材料)の摂取する。
乳製品(牛乳、ヨーグルトなど)、大豆製品(豆腐、納豆など)、小魚類(干しエビ、シシャモなど)、野菜(小松菜、青梗菜など) - ビタミンD(カルシウムの吸収を助ける)を摂取する。
きくらげ、ウナギのかば焼き、サケ、サンマ、太刀魚など - ビタミンK(カルシウムを骨に定着させる)を摂取する。
納豆、ニラ、ほうれん草、ブロッコリーなど - タンパク質(骨の質を高める)
肉、魚、卵、乳製品、大豆製品など
⑥定期的な検査と治療を受けよう
(男性)70歳以降は定期的に測定しましょう。
(女性)閉経後は原則として年1回、自治体の節目検診を利用しましょう。
この6つのポイントを意識しながら、生活習慣を改善していきましょう!




次回の第4回成人講座は、「蓄音機コンサート」です。
昭和25年製の手回し式蓄音機を使って、昭和34年までの日本の流行歌を約20曲、聴かせていただく予定です。歌手で言えば、石原裕次郎、美空ひばり、三橋美智也、島倉千代子など、どんな曲が聴けるのかは、当日のお楽しみです。
申込期間は9月1日(月)から9月23日(火、祝)の間です。皆さん、ぜひお申し込みください!!